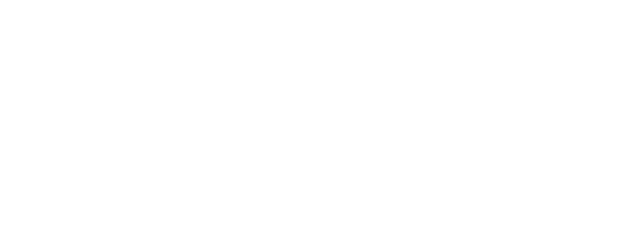Hi-STANDARDを中心に企画された音楽フェス「AIR JAM(エアジャム)」の隆盛にはじまり、デビロックやマックダディといったバンド発のアパレルブランドの台頭や彼らを中心に形成された“恵比寿系”と呼ばれるクロスカルチャーシーンの流行など、《あんときのストリート》はバンドシーンからの影響を色濃く受けた時代でもありました。
そこで今回は、当時から続くバンドシーンのアーティストを撮影するフォトグラファーの橋本塁くんをゲストに迎え、当時の思い出が詰まったプレイリストとともに《あんとき》の音楽の魅力を振り返っていきたいと思います。
写真展&ライブイベント「SOUND SHOOTER」やアパレルブランド「STINGRAY」の主宰者として人気を博す塁くんですが、実は過去に「ollie」の社員カメラマンとして、我々と一緒に雑誌制作の仕事をしていたことも! そんな訳で、ざっくばらんによもやま話を繰り広げさせていただきました。
PROFILE / 橋本塁(はしもと・るい)
1976年北海道生まれ。大学卒業後、24歳のときにジーンズのパタンナーからカメラマンに転身。雑誌「ollie」の社員カメラマンを経て、2005年にフリーランスに。HAWAIIAN6やELLEGARDEN、ストレイテナーやONE OK ROCKといったさまざまなバンドの撮影を担当。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」では、メインステージのオフィシャルカメラマンも務めた。2006年より、写真展&ライブイベント「SOUND SHOOTER」を開催。水玉をコンセプトとしたアパレルブランド「STINGRAY」のプロデュースも手がける。
SOUND SHOOTER 橋本塁が選ぶ《あんとき》のプレイリスト
当時よく聴いていた思い出の曲やAIR JAM世代ならハズせない歴史的名曲など、《あんとき》の時代の空気感がヒシヒシと伝わってくるプレイリストを塁くんが作成してくれました。今回の対談では、このプレイリストをもとに話を進めています。
野田:今日は忙しい中、時間を作ってくれてありがとう!
橋本:名古屋で開催した「SOUND SHOOTER」の写真展に遊びに来てくれたとき 以来だよね!
野田:いきなりズケズケと4人で押しかけちゃってゴメンね(笑)
遠山:完全に招かれざる客だったよね(笑)
橋本:今日は《あんとき》を振り返るってことで、いろいろとCDを持ってきましたよ〜


塁くんが持ってきてくれた《あんとき》のCDたち
遠山:うわ〜懐かし〜! このライフボールの12ch『STEP WISE』は、チープな手描き感が香ばしくて当時思わずジャケ買いしたな〜
橋本:個人的には、サイガンテラーの『MARCH OF SAIGAN』が思い出深いですね(笑)
高柳:メンバーの方が編集部で働いていましたもんね
遠山:おっ! 『THE ULTIMATE FAST BEAT』もある。これって、ラフィンノーズからスーパー・ステューピッドなんかまでが参加した新旧クロスオーバー的なオムニバスなんだよな〜
橋本:たしか、これがスーパー・ステューピッドの初音源なんですよね。まだドラムの浩さんが参加する前で、LOW IQ 01さんとジャッキーさんの2人だけの時代。このオムニバス自体は、アクションスポーツブランドのISLAND SNOWが日本に上陸した記念にリリースされたんですよね
遠山:そうなんだ。当時のメロコアは、スノーやスケートとの結びつきが強かったよね。雑誌「Fine」でもよく紹介されていたし
高柳:NOFXやバッド・レリジョンも、スノーやスケートのシーンから出てきたイメージありますね。当時のスノーやスケートのビデオBGMにメロコアがよく使われていましたし
野田:これ(『FAR EAST HARDCORE』)は、ZOZOTOWNを取り上げた記事でも紹介されていなかったっけ?
遠山:そうそう。GMFやスイッチスタイルが収録されている。この『A SHORT STORY』って、どんなコンピなんだっけ?
橋本:SPICE OF LIFEの1枚目のコンピです。一時期、すごい高値になっていたんですよ
遠山:あっ、そうだそうだ! スプロケ(SPROCKET WHEEL)とかハスキン(HUSKING BEE)なんかに加えて、意外にもスネイル(SNAIL RAMP)が参加していたんだよね! 懐かしい!!
橋本:開始早々でかなり盛り上がっちゃったけど、このテンションで続くかな〜(笑)
野田:では、CDの話はこの辺にして、さっそくプレイリストを振り返っていきましょうか!
まずは、2000年代初頭のバンドシーンを盛り上げた人気3バンドの紹介から
高柳:今日は塁くんが作ってくれたプレイリストの曲を通して、《あんとき》のシーンの熱気を思い起こしたり、当時の思い出話なんかに花を咲かせたいと思っているんだけど、まず冒頭に選んでくれた3曲は、塁くんがいつくらいによく聴いていた曲になるの?

(左から)the band apartがブレイクするきっかけとなったセカンドシングル『Eric.W(エリック・ダブリュー)』、HAWAIIAN6の1stミニアルバム『FANTASY』、DOPING PANDAの記念すべき1stアルバム『Performation』
橋本:これはollie編集部に入った2001年の前後くらいによく聴いていた曲だね
遠山:えっ、橋もっちゃんってそんな早くから編集部にいたっけ?
橋本:たしか(ollieを制作していた)ミディアムの入社は、2001年の6月くらいだったハズです
遠山:HAWAIIAN6って、もう少し後にブレイクしたイメージがあったんだけど
橋本:そうですね。この頃は、ピザ(PIZZA OF DEATH RECORDS)に移籍してブレイクする前の黎明期です。ステップ・アップ・レコーズという小さなレーベルに所属していて、DOPING PANDAやSTOMPIN’ BIRD、LEGGOといったバンドと一緒に対バンしていましたね。世代的には、第3次AIR JAM世代になるので
遠山:それはハイスタやハスキン、バックドロップ(Back Drop Bomb)あたりを第1次世代とするならってこと?
橋本:芸人さんみたいな表し方になって申し訳ないんですが(笑)、ハスキンやバックドロップ、リーチあたりは、正確には1.5世代くらいになるんじゃないですかね
遠山:そっか、スーパー・ステューピッドとかコークヘッド(COKEHEAD HIPSTERS)あたりまでが第1次世代か
橋本:はい。AIR JAM 2000が開催された日もACB(※新宿のライブハウス)でやってたHAWAIIAN6のライブを撮影してたんですが、お客さんがガラガラで「今日はみんな向こう行ってるね〜(笑)」なんてMCしていたのを思い出しますね〜
瀬戸:僕もこのアルバム(『FANTSY』)はリリースされてすぐに購入したんですが、「とんでもなくカッコいいバンドが出てきたな〜」と衝撃を受けましたね
橋本:ブレイク前とはいえ、数万枚は売れたからね〜
遠山:当時の音楽シーンのスゴさを感じさせるエピソードだね。良くも悪くも「出せば売れる」が通用した時代だよね
瀬戸:当時も新宿のタワーで猛プッシュされてましたよね
橋本:そうそう。当時のタワーは渋谷店と新宿店のインディーズのバイヤーが結構な力を持っていたんだけど、その担当者がHAWAIIAN6を気に入っちゃって。それで猛プッシュされていたんだよね。それぞれの店舗で推すバンドもマチマチだったから、当時はいかにバイヤーに気に入られるかが重要だった。それとタワーって、POPを作る事業部も別にあるんだけど、そこの担当者もHAWAIIAN6を気に入っていたから、タダでどんどんPOPを作ってもらえたこともセールスにつながっていたと思うよ
一同:へ〜! そんなことがあったんだ!!
瀬戸:同時期にモンパチ(MONGOL800)のデビューアルバムが出てて、一般的にはそっちの方が派手にブレイクしていましたが、タワーでは完全にHAWAIIAN6推しでしたもんね。
【#HAWAIIAN6】ミニアルバム『The Brightness In Rebirth』入荷致しました。(菅野)https://t.co/lrA9KXQv3s#CD入荷情報 pic.twitter.com/4o4K7G5OOH
— タワーレコード渋谷店 (@TOWER_Shibuya) March 24, 2020
ちなみにタワーのHAWAIIAN6愛は現在も続いている模様。こちらは2020年にリリースされたミニアルバム『The Brightness In Rebirth』の入荷時期の様子。
高柳:スタッフたちの忖度のない、リアルなリコメンドによってムーブメントが生み出されるのって、《あんとき》の特徴ですよね!
橋本:本当そうだよね
遠山:この頃ってハイスタを筆頭に、メロコアやパンクのシーンが一気に盛り上がった時期だったから、「次にブレイクするのはどのバンドなんだろう?」って注目も集まっていたし、みんなが“次のハイスタ”を探してたよね
橋本:一方、こうしたシーンとは別に、アンリミテッドレコードがスポンサーをしていた「HANG-OUT(ハングアウト)」というTV番組によって作られたシーンもあったんです。175RやB-DASH、シャカラビッツあたりがその代表バンドになるんですが、そこから出てきたバンドのひとつが(3曲目の)バンド・アパートになんですね。他のバンドがメジャー感のあるインディーズという立ち位置で活動を行う中、バンド・アパートだけは独創的で謎めいた感じの音楽を発信していたので、かなり注目が集まりましたね
当時、テレビ東京で放送されていた「HANG-OUT」には、DBXの大野さんやB×HのHIKARUさんなども出演し、番組を盛り上げていた。YouTubeに残されていたこのアーカイブには、ファッション誌でモデルとして活躍していた井出大介さんとともに東京ストリートシーンのOG、高木完さんが出演!
遠山:そもそも、音楽性も全然違うよね。メロコアって、シーンのことを全然知らない人が聴いたら、全部一緒に聴こえてたんじゃないかと思うくらい節まわしが一貫してたじゃない?ほとんどが刹那系のマイナーコードを速いツービートでやっているというか
橋本:たしかにやっていることはシンプルでしたよね。でも、そこにファッションやカルチャーが結びついていたから、《あんとき》のシーンは面白かったというのはありますよね
高柳:この時代のバンドの人たちって、音楽性はもちろん、ファッション的にもお洒落な人がめちゃくちゃ多かったですよね。カルチャー偏差値がズバ抜けて高いといいますか
野田:そこはジャケットひとつとっても、スゴい伝わってくるよね。当時は気合いもお金もめちゃくちゃかけていたし。今だとサムネ画像のひとつっていう感覚なのかもしれないけど
遠山:ジャケ買いという文化が残っていたのも、この時代までだよね
橋本:この辺のジャケは、家に飾りたくなるようなデザインですよね。それと、ライブのフライヤーもひとつのカルチャーを形成していましたよね。「これ、誰が作ったフライヤー?」って、作り手にまで注目が集まっていましたし
高柳:《あんとき》の音楽シーンがあそこまで盛り上がったのって、ストリートというカルチャーとの結びつきが強かったからなんでしょうね
塁くんがカメラマンを志したきっかけと、勢いで入った当時のollie編集部について
遠山:やっぱり、橋もっちゃんがカメラマンになろうと思った動機って、この辺のバンドを撮りたいからだったんでしょ?
橋本:ミディアムに入社する前は、ジーンズのパターンナーとして働いていたんですけど、シェルターで初めて観たHAWAIIAN6のライブにいたく感動して、そのときにたまたま持っていた「写ルンです」で写真を撮ったんです。それがきっかけで写真の魅力に引き込まれて、カメラマンを志そうと思いました
高柳:じゃあ、カメラマンとしての原体験はHAWAIIAN6のライブなんだ?
橋本:そうそう。それで求人情報誌を開いてみたら、偶然にもミディアムの社カメの求人が掲載されていたので、応募してみようと思って
遠山:すぐに採用されたの?
橋本:そうですね。その半年後にはカメラマンになってました
遠山:時流に乗れてんな〜(笑)。じゃあ、カメラ経験ゼロで入社したってこと?
橋本:そうなりますね(笑)。でも、そんな感じで入社したもんだから、(当時ミディアムにあった)スラッシャージャパン編集部からブツ撮りの依頼をされたときに、「え、ブツ撮りって何ですか?」って聞き返して、「誰だよ、こんなヤツ、入社させたの~!」ってバカでかい声で叫ばれたりしてツラかった……(笑)。その後、先輩カメラマンに教わってできるようになっていくんですが
高柳:当時の編集部は、未経験でいろんな人を採用していましたもんね
野田:技術職であるカメラマンを未経験で採用するってすごいな(笑)
遠山:とはいえ、橋もっちゃんとしては、やっぱりollieのカメラマンになれば、自分の好きなバンドを撮影できると思ってたんじゃないの?
橋本:正直、当時はそこまで考えられてはいなかったですけど、やっぱり「AIR JAM」に出ていたバンドが表紙を飾っていた雑誌だったんで、チャンスがあれば挑戦したいな、くらいには思っていましたね

「AIR JAM」の常連バンド、ハスキング・ビーが表紙を飾った1998年11月号の『ollie』。ちなみにこのollieは、遠山さんが初めて制作に関わった記念すべき号でもあります
遠山:でも、いざ入ったら、洋服のブツ撮りばっかりやらされたと(笑)
橋本:ですね(笑)。詳しくはなかったですが、洋服自体は好きだったので、楽しかったですけどね。常に新しいことを吸収できましたし、仕事が早く終われば、バンドの撮影にも行けましたし
遠山:じゃあ、その頃はファッションの撮影がメインで、趣味でバンドを撮影してたわけだ
橋本:そうです。そうやって趣味でライブ撮影を続けるうちに、当時、ミクスチャーシーンで人気のあったフルゲインというバンドがメジャーに移籍することになって、初めて音楽専門誌に掲載する写真を撮影してほしいという依頼を受けたんです。そこからライブ撮影も仕事として請け負う機会も増えていきましたね
時はさかのぼり、塁くんが青春時代を過ごした北海道のメロコアシーンへ
高柳:では、続けてプレイリストの次の曲へと進んでいきたいんだけど、次の4〜8曲目くらいは、ちょっと時間がさかのぼる感じだよね。この辺はollieでカメラマンをやる前によく聴いていた曲なのかな?
橋本:そうだね
高柳:さっきの話でいう、AIR JAMの第1世代のバンドたち?
橋本:そうだね。ショートサーキットだけはちょっと新しくて、第2世代になるのかな
高柳:塁くんにとって憧れのバンドたちになるの?
橋本:ollieに入る前はもちろん、もっと言うと、その前の大学時代からめちゃくちゃライブ行ってたねバンドだね
遠山:橋もっちゃんって、大学で上京してきたんだっけ?
橋本:そうです。一浪したんで23歳で大学を卒業しているんですが、東京に出てきたのは大学3年生のときです。なので、最初の2年は北海道、後の2年を東京で過ごしました。特にこの辺のバンドを聴いていたのは、18~21歳くらいですかね
遠山:北海道だと、この辺のバンドってどんな流行り方をしていたの?
橋本:北海道には「NO MATTER BOARD」っていうローカルのスノーボード番組があるんですが、北海道のスノーボードシーンに絶大な影響力を持っているんですね。そこで当時、オフスプリングとかハイスタをガンガン流していたので、感度の高いボーダーたちからまずは火がついた感じでしたね
遠山:「スノーボード=メロコア」というイメージを作り上げてたんだ
橋本:そうです。それと当時は「Fine」とかの雑誌の影響も強かったから、若い子の間でボードカルチャーが人気あったというのもありますね。だから北海道だと、スノーボードをやっている子が多かった
現在も続く、北海道テレビの人気番組「NO MATTER BOARD」。過去にはエンディングテーマ曲をハスキング・ビーが担当したことも。1999年からはメロコアシーンのバンドたちとともに、「NO MATTER LIVE」というライブイベントも開催している
遠山:なるほどね。北海道だと、スノーボードを経由してこういう音楽が知られるようになっていったんだ。バートンが全盛の時代で、ストーミーのステッカーを貼っていることが自慢できる時代だったよね〜
橋本:横山健さんもギターに貼ってるくらいでしたからね〜。だから、当時ストーミーで働いていたモブスタイルの田原さんとか、とんでもなくすごい人なんだろうなって思って雑誌を読んでいましたよ
高柳:田原さんはストーミーのフラッグタワーの中にあったスタジオで、HIKARUさんたちとラジオ番組なんかもやってましたよね
遠山:なんせ、AIR JAMの名物MCだからね!
橋本:そうですよ! だから、いまだにフジロックのステージMCは田原さんがやってますよね
遠山:そうか、橋もっちゃんはその世代なのか〜。そりゃあ、ガッツリ影響受けるよね。でも、当時盛り上がってたとはいえ、北海道だと人気はごく一部だったんじゃない?
橋本:真心ブラザーズやミッシェル・ガン・エレファントくらい有名なギターロックバンドになると、ペニーレーン24とかのライブハウスには来ていたんですが、それよりもマイナーなインディーズバンドになるとほとんど来ることはなかったですね。この辺のバンドが来るようになったのは、SLANGのKOさんがカウンターアクション(※ライブハウス)を作ってからですね
高柳:じゃあ、この辺のバンドは塁くんが北海道にいた頃からライブを観てたんだ?
橋本:そうだね。コークと一緒にやったスーパー・ステューピッドの初めての北海道のライブも、ハイスタの全国ツアーも、カウンターアクションで観たよ
高柳:ちなみに、そのカウンターアクションというライブハウスを作ったKOさんのSLANGってバンドは、プレイリストの11曲目に入っているバンド?
橋本:そうそう。札幌ハードコアシーンの中心的バンドで、IN MY BLOODっていう洋服のブランドもやってたから、ollieにもよく出ていたよ
野田:地元の雄だもんね。北海道取材では、リサーチなんかでよくお世話になりました
橋本:当時、ハイスタが北海道でライブするときは、SLANGと一緒にやることが多かったし、2018年にやったハイスタの全国ツアーでもカウンターアクションでライブしてたからね

カウンターアクションで撮影されたSLANGのKOさんと塁くんのツーショット
高柳:じゃあ、10曲目のイースタンユースと並んで、地元を代表するバンドなんだ?
橋本:そうそう。ブラッドサースティ・ブッチャーズ、イースタンユース、怒髪天がいて、その2、3歳下にKOさんがいた感じかな。みんな東京行っちゃったけど、KOさんだけはずっと札幌を守ってるんだよ
バンド界隈から誕生した当時のアパレルブランドと、塁くんのブランド「STINGRAY」の共通点
野田:でも、この辺のバンドが好きだった割に、塁くんってあまり恵比寿系のブランドの服を着ていたイメージないよね?
橋本:デビロックの6万円くらいするダウンジャケットを、清水の舞台から飛び降りる思いで買ったことはあったけどね(笑)
遠山:当時のこの辺のバンドの人たちって、ビラボンとかセッションズといったスケートやスノーのブランドの服を着ていたし、そこまでドメスティックのブランドを着なくちゃって感じでもなかったんじゃない?
橋本:ですね。実際、恵比寿系ファッションの台頭って、この界隈のバンドブームの少し後だったのもありますしね。
瀬戸:この辺のバンドの早い人たちは、2000年くらいからすでに洋服作りに専念していましたよね。出せば即完売するくらいの人気でしたし
高柳:塁くんもSTINGRAYっていう洋服のブランドも手がけているけど、当時のバンドの人たちのブランドから影響を受けてたりもするの?
橋本:デザイン的な影響は受けていないんだけど、自分以外のメンバーがチャットモンチーやリディムサウンターというバンドをやっていたアーティストだったから、「音楽好きの人に向けたブランド」というコンセプト的なところでは影響を受けたかもしれないね。当時も音楽系の洋服ブランドとファッションブランドは、本業と副業くらいの明確な差があったと思うんだけど、STINGRAYも立ち位置としては前者なので、そこはブレることなくやっていきたいと思っているよ
野田:でも、そのイメージをブレることなくキープできているブランドって少ないよね
橋本:STINGRAYはWEBとポップアップだけで販売する小規模展開だからキープできているかもしれないけど、やっぱり、本業として事業を起こして、展示会や卸しをしてたくさんの商品を販売していくとなると、ビジネスが優先されるから難しくなってくるよね
会場での販売にこだわったSTINGRAYのPOP UPの様子 – タップすると連続再生で観れます / ザッピングを使用
野田:たしかにそれがダメになる原因だよね。当時のバンドTじゃないけど、現場に行かないと買えないっていうのは、今の時代でもすごく魅力的な要素だよね。これだけ情報がある時代だから、逆に不便が価値になるというか。そこまで苦労して買ったら絶対にSNSとかで発信したくなるし
橋本:当時はそれが当たり前だったからね。「どこどこでなになにが販売されるらしいよ」って情報も、噂として広まるようなレベルだったしね
野田:そうした話題性や希少性を維持するなら、副業くらいの感覚じゃないと無理かもね
遠山:さっきのタワレコのリコメンドの話もそうだけどさ、当時は雑誌も含め、人の力で発信されたアナログな情報しかなかったから、そういった数少ないメディアに力が集中していたし、みんなそれを頼っていたところがあったけど、今のネットの時代は情報が分散しすぎちゃって、ブランドの世界観を維持するのは本当に難しくなっているよね
最後は、ずっとインディーズレーベルのようにカメラマンを続ける、塁くんの仕事哲学にまで話は展開
遠山:話は戻るけどさ、そうやって橋もっちゃんはollieの仕事と並行して、ライブの写真を撮影してたわけじゃない? ミディアムを辞める頃には、この辺のバンドとは仲良くなっていたの?
橋本:めっちゃ仲良かったですよ。プライベートでは、友だちみたいな間柄になっていたので
遠山:やっぱり、撮り続けていれば、喋るようになるし、仲良くなるもんなんだね
橋本:仕事じゃなかった分、なおさらでしたね
遠山:当時、よく撮影していたのは、どの辺のバンドになるの?
橋本:HAWAIIAN6やバンド・アパート、DOPING PANDAやSTOMPIN’ BIRD、あとはロング・ショット・パーティーとか。それこそ、ホルモン(マキシマムザホルモン)も撮ってたし、NOBってバンドも撮ってましたね
遠山:当時からその辺のバンドは新世代な感じがしてたんだ?
橋本:そうですね
遠山:ミディアムを辞めるときには、この辺のバンドを撮影して食べていこうっていうプランはあったの?
橋本:ミディアム時代の後半には結構いろいろなバンドを撮影するようになっていたので、もっと全力でバンドに密着して撮影したいという想いはありました
遠山:それで写真集を発売して独立した感じ?
橋本:写真集はちょうどその当時、フローラルウォーターというブランドにいたスタイリストのヨコペン(横田勝広)が、チェンバロのメンバーを起用した「STRIDE」っていうスニーカーブランドのプロモーションの仕事をしていたこともあって、彼に「写真集を出して一緒にやろうよ」と誘われたのがきっかけですね。3000部くらいのセールスがあったので、当時としては売れた方だと思うんですが、それ以上に作りすぎちゃって、気づいたら、300万円くらい借金を背負ってました(笑)。フリーになった瞬間、地獄を味わいましたね〜(泣)
一同:大爆笑!
遠山:とはいえ、その後の営業ツールにはなったでしょ?
橋本:そうですね。でも、当時はライブカメラマンという職業もまだ確立されていなかったので、先行してハイスタやブラフマンを撮っていたツカサ(三吉ツカサ)とかTEPPEI(岸田哲平)に追いつくには、彼らがまだ出していない写真集を出すしかないと思っていたところもありましたね
全22バンドの2000年代前半のレアなライブ写真が収録された写真集『LOVE』 – タップすると連続再生で観れます / ザッピングを使用
遠山:ちなみに、借金はどうやって返したのよ?
橋本:絶望の最中、何かしないといけないと思って、翌年に「SOUND SHOOTER」という企画でライブイベントと写真展を開催しました
遠山:Zepp Tokyoで開催したやつ?
橋本:そうです。その頃、よく撮影していたELLEGARDENやSTRAIGHTENERなんかに出演してもらって。おかげで一発で借金を返すことができました。mixiや2ちゃんでは、「裏方のくせして、しゃしゃり出て来るんじゃねー」みたいな陰口を散々叩かれたりはしましたが……(笑)
高柳:いや、すごいでしょ! 塁くんがピンチだから、みんなが「協力しようぜ!」って思ってくれたわけだし。塁くんの人徳のなせるワザだと思うけどね
野田:本当だよね。写真のテクニック云々より、まずは人柄というか (笑)
橋本:たしかに(笑)。ミディアム時代も、編集部員から写真の良し悪しでオファーを受けたことは一度もないから(笑)。やりやすさとアホさとフットワークの軽さで重宝されてたタイプ
高柳:でも、フリーランスになると、そこが大事になってくるよね
橋本:カメラマンはテクニック以外にも必要とされる素養があることをミディアムでみっちり教え込まれたからね(笑)。中でも、写真は自分が撮りたい絵を撮るんじゃなくて、担当者や発注者が欲しい絵を撮らないといけないという鉄則は、ライブカメラマンになってからもすごく役立ったよ
野田:ライブカメラマンって作家性とかアーティスト性で勝負するイメージが強いんだけど、塁君は自分が撮りたい写真を撮るんじゃなくて、バンドが望む写真を撮っているんだ?
橋本:そう
野田:そのスタンスでやってたら、重宝されるよね〜。でも、そうやって人気が出て、大御所に上り詰めれば、逆に塁君が撮りたい写真を撮っても喜ばれるんじゃないの?
橋本:かもしれないね〜。それをしていないから俺は大御所になっていないのかも(笑)
野田:イヤイヤ、いまや大御所でしょ。塁君に撮ってほしいという若手バンドも多いんじゃない?
橋本:その需要が一番多かったのは10年くらい前だよ。「HAWAIIAN6やELLEGARDENを撮っている塁さんに撮影をお願いしたい」というオファーをいただいていたのは
遠山:やっぱり、そういうときはまず説教垂れるの(笑)? お前らにはまだシャッター押せねーわ、俺の指がまだ動かないんだよ!とか(笑)
一同:大爆笑
橋本:そんなことは一度も言ったことありませんよ(笑)!
遠山:撮影当日にいきなり「今日のお前ら撮りたくないわ」とか言ってほしいよ(笑)。でも真面目な話、求められているものに対して一生懸命に応えるのって、ときにはキツいしストレスになることもあると思うんだけど、撮られる側が盛り上がってくれれば、それが一番カメラマン冥利に尽きるってことだもんね。こうした積み重ねが、やっぱり大事なんだろうね
橋本:そうですね。でも一方で、最初から作家性を強く打ち出しても、売れることができたら、ずっとそのスタイルを突き通せるとは思うんですが
高柳:ハマればいいけど、ハマらなかったら大きくハズすことにもなっちゃいそうだよね
遠山:今の時代はハマるのが難しい時代だからね。それしかできない人と思われちゃうのも逆に嫌だしね
橋本:実はさっき話した、「ELLEGARDENを撮っている塁さんに撮影をお願いしたい」というオファーをしてくれたバンドって、当時初めてLOFTでワンマンライブをすることになったONE OK ROCKだったんですよ。そのときの縁でいまだに撮影させてもらっているのは、やっぱり自分がメンバーと接しやすいスタンスでいるからというのが大きいと思うんですよね。彼らが大きい会場でライブをするときには、それこそ作家性の塊のようなイケイケのカメラマンと撮影が一緒になることもあって、その作品の出来栄えに正直ヘコまされることもあったんですけど、自分の中では「カメラマンは長く生き残ってなんぼ」という考え方に価値を見出すようにして、今まで続けてきていますね
遠山:橋もっちゃんが最近注目している若手のバンドっているの?
橋本:僕が今好きで撮らせてもらっているのは、FOMAREっていうスリーピースのロックバンドです。小学生の頃にモンパチとかハワイアンを聴いて育った世代で、群馬県高崎市のバンドなんで、G-FREAK FACTORYのイベントにも通っていたみたいです。売れそうなバンドを撮りたいというよりも、自分が好きになったバンドを長く撮り続けたという気持ちが強いのは、昔からずっと変わりません。何年かに一度、ずっと密着して撮りたいなと思えるバンドとの出会いがありますね

遠山:そこは音楽好きのサガなんだろうね。橋もっちゃんがバンドを撮りたい原点はそこにあるんだと思うし。今後はカメラマンとしてこうありたい、みたいな展望ってあったりするの?
橋本:長い間撮影させてもらっているバンドでも新しい刺激を求めるなら、当然違うカメラマンに撮影してもらおうとするはずなんです。自分たちが変わらない分、外部からの新しい刺激でリブートするのは正しい考え方だと思いますし。じゃあそのとき、自分のようにキャリアの長いカメラマンはシーンにどんな貢献ができるかといえば、それは若いバンドに彼らの憧れのバンドの痕跡を伝えることだと思うんです。《あんとき》を撮影していた自分を起用してもらえれば、その頃のケーススタディを教えることができるといいますか
野田:ある意味で育成だね (笑)
橋本:育成というと大袈裟かもしれないけど、たとえば、ハワイアンが好きなバンドがいたら、彼らが10代後半くらいのときにはこんな感じのスタイルでやってたよって伝えられるかなと
遠山:《あんとき》の語り部のような役回りだね
野田:塁くんなら説教臭くならなそうだしね
橋本:ここまで長いことライブカメラマンをやってると、もう辞めて別の仕事をしてもいいなと思うこともいっぱいあったんですが、今はもう後に引けなくなってきたところもあるんで。バンドでたとえるなら、めっちゃ売れてるわけでもないけど、解散するタイミングも逃してしまったような感じ(笑)。マイペースに続けていこうと思っています
遠山:橋もっちゃんのカメラマン人生は、バンド活動に近いわけだね
橋本:近いと思います。ずっとインディーズのレーベルみたいな感じですね。ハワイアンもピザに移籍して、二、三十万枚売れた時期もありましたけど、今は少数のスタッフで自分たちのペースを守りながらやっていますし。それをお手本にやっていきたいですね。自分が初めて撮影したバンドの哲学が、そのまま自分の仕事哲学になっているという(笑)
一同:塁くんらしい生き方だね!
HAWAIIAN6やDOPING PANDAといった’00年代を熱狂させたバンドのエピソードに始まり、塁くんのライブカメラマンとしての生き方にまで話が及んだ今回の対談はいかがだったでしょうか?
もっと音楽の話で盛り上がるのかと期待していた読者の方たちにはスミマセン! でも、《あんとき》のバンドシーンが教えてくれた音楽のカッコ良さを記録し続けるだけでなく、自身でも体現する塁くんの生き方には、僕たちもあらためて大きな刺激を受けたのでした!
 日本語
日本語 English
English 韓国
韓国 中国(简体)
中国(简体) 中國(繁體)
中國(繁體)